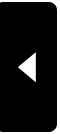マットソニックは釣れるのか?
雑誌 Anglingの6月号、101p「それゆけ小林重工」の記事、ちょうどマットソニックについて取り上げてます。
マットソニックというのは、端的に言って小林重工CEOの小林良彰氏が提唱するところの「魚の意識に訴える要素」。
「魚の意識」と言えばなんだか「?」なんだけれど、要するに「反射」や「反応」に基づいた魚の生態の一部と言えそうです。
そしてこの理論の中核を成すのは「魚が側線で感じていることがら」のようですね。
私自身はその昔、ブラックバスのトップウォーター関連の記事として取り上げられていたことからこの理論の存在を知っておりました。
当時の記事はかなり読める、説得力のある物だったと思います。
>Anglingの記事よりも
マットソニック理論、これを考えに入れて釣りをすると、管理釣り場でも釣果が上がるのだろうか?
ちと考えてみませんか?
▼いいやいらん▼他の釣り系ブログへ行く



マットソニックというのは、端的に言って小林重工CEOの小林良彰氏が提唱するところの「魚の意識に訴える要素」。
「魚の意識」と言えばなんだか「?」なんだけれど、要するに「反射」や「反応」に基づいた魚の生態の一部と言えそうです。
そしてこの理論の中核を成すのは「魚が側線で感じていることがら」のようですね。
私自身はその昔、ブラックバスのトップウォーター関連の記事として取り上げられていたことからこの理論の存在を知っておりました。
当時の記事はかなり読める、説得力のある物だったと思います。
>Anglingの記事よりも
マットソニック理論、これを考えに入れて釣りをすると、管理釣り場でも釣果が上がるのだろうか?
ちと考えてみませんか?
▼いいやいらん▼他の釣り系ブログへ行く

(マットソニック理論に関し、私の思い違いがあれば勘弁いたたいた上、どうぞご指摘くださいね)
実際のところ、ネットで引いてもすでにいくつかのマットソニック関連の記事があります。
鱒関連だってすでにビデオになっているようです。
ご興味があればググってみてください。
ところで、私が思いますにマットソニック理論そのものを突き詰めますと、もっとも釣果を上げられるのはその魚が食っているライブベイト「生き餌」を使うことに他ならないことになりげに思います。
どうもここからは逃れようがありません。
そういう意味で言えば、フライというのは昔からマットソニックとしてもしかすると完成状態にある方法論のようにも思えます。
でまあ、ルアーの世界に話を戻しますと、いかに「生き餌」に近いルアーを作るかという部分に心血を注いできたという歴史がルアー作りの一分野にはありました。
ただそこで、マットソニック理論を知る者としては、あくまで人間の目でみたリアルな人工餌としてのルアーでなくて、「魚の意識」からしていかに餌らしくあるかというのが重要なポイントであることは見過ごせません。
人間の目で見ていくらリアルな小魚のルアーでも、魚から見れば(マットソニック的に)意味のわからない不思議な物体と写るだろうということです。見た目だけでなく、側線的にですね。
そして更に、人間の知恵として合理的なマットソニックとしては人間の目でどう奇天烈(きてれつ)に見えようが魚の意識としてマットソニックに合致した物であるかが重要となるでしょう。
むしろ、今までのルアーのデザインの常識からはずれるほどに釣り人が喜ぶということに面白さを見いだしているようにも思えます。
■マットソニックで釣れたのだろうか?
ところが、私にはどうしてもわからん部分があります。
それは・・
フィールドへ出て「これぞ」と思われるマットソニッックなルアーを使って釣りをしたとしましょう。
それで他のスプーンやクランクよりも釣れたとしましょうや。
この結果だけを持ってしてマットソニックなルアーがマットソニックとして魚に意識されて釣果が上がったのでしょうか?
もしかすると、マットソニッックとは関係ない部分の要素で釣れているということはあり得ないのでしょうか?
検証方法ってあるんでしょうか?
■楽しみと釣果のはざま
それから、ことにブラックパスをトップでわざわざ釣るというタイプの楽しみ方においては、そもそもが「餌に見えない何物か」そしてひいてはできるだけ「マットソニック的でない物」で釣ることにそもそも楽しみがあるということもありはしないかと思われます。
だから、トップオンリーのバス釣りは伊達酔狂な本当の遊びとしての遊びだと思うのです。
そういえば・・・・ガキの頃フライをやってるときのこと
新しいフライを入手すると、風呂に水中眼鏡をして入り、浮かしたフライを水中から見上げて「見え加減」を研究してました。
そんときに思ったのは・・・
「あ、オレ自身は魚じゃないから、魚にはどう見えているのかわかんないよな」
管理釣り場で「マットソニックなあ・・・」とつぶやいた今日この頃。
▼売れ筋トラウト用ハードルアー
実際のところ、ネットで引いてもすでにいくつかのマットソニック関連の記事があります。
鱒関連だってすでにビデオになっているようです。
ご興味があればググってみてください。
ところで、私が思いますにマットソニック理論そのものを突き詰めますと、もっとも釣果を上げられるのはその魚が食っているライブベイト「生き餌」を使うことに他ならないことになりげに思います。
どうもここからは逃れようがありません。
そういう意味で言えば、フライというのは昔からマットソニックとしてもしかすると完成状態にある方法論のようにも思えます。
でまあ、ルアーの世界に話を戻しますと、いかに「生き餌」に近いルアーを作るかという部分に心血を注いできたという歴史がルアー作りの一分野にはありました。
ただそこで、マットソニック理論を知る者としては、あくまで人間の目でみたリアルな人工餌としてのルアーでなくて、「魚の意識」からしていかに餌らしくあるかというのが重要なポイントであることは見過ごせません。
人間の目で見ていくらリアルな小魚のルアーでも、魚から見れば(マットソニック的に)意味のわからない不思議な物体と写るだろうということです。見た目だけでなく、側線的にですね。
そして更に、人間の知恵として合理的なマットソニックとしては人間の目でどう奇天烈(きてれつ)に見えようが魚の意識としてマットソニックに合致した物であるかが重要となるでしょう。
むしろ、今までのルアーのデザインの常識からはずれるほどに釣り人が喜ぶということに面白さを見いだしているようにも思えます。
■マットソニックで釣れたのだろうか?
ところが、私にはどうしてもわからん部分があります。
それは・・
フィールドへ出て「これぞ」と思われるマットソニッックなルアーを使って釣りをしたとしましょう。
それで他のスプーンやクランクよりも釣れたとしましょうや。
この結果だけを持ってしてマットソニックなルアーがマットソニックとして魚に意識されて釣果が上がったのでしょうか?
もしかすると、マットソニッックとは関係ない部分の要素で釣れているということはあり得ないのでしょうか?
検証方法ってあるんでしょうか?
■楽しみと釣果のはざま
それから、ことにブラックパスをトップでわざわざ釣るというタイプの楽しみ方においては、そもそもが「餌に見えない何物か」そしてひいてはできるだけ「マットソニック的でない物」で釣ることにそもそも楽しみがあるということもありはしないかと思われます。
だから、トップオンリーのバス釣りは伊達酔狂な本当の遊びとしての遊びだと思うのです。
そういえば・・・・ガキの頃フライをやってるときのこと
新しいフライを入手すると、風呂に水中眼鏡をして入り、浮かしたフライを水中から見上げて「見え加減」を研究してました。
そんときに思ったのは・・・
「あ、オレ自身は魚じゃないから、魚にはどう見えているのかわかんないよな」
管理釣り場で「マットソニックなあ・・・」とつぶやいた今日この頃。
▼売れ筋トラウト用ハードルアー
この記事へのコメント
こんにちは。
マッドソニック論・・・
私が思うに、究極?!は、『動かす(側線を刺激)』か、『何もしない(視覚を刺激)』か、ですかね。
同じコンディションで、同じルアーを投げて、一方は『リトリーブ』、もう一方は『ホットケ』、でどちらがお魚を良く誘うか?
多分状況(プレッシャーとか)によって、マチマチになると思いますが・・・(笑)
人間は振動を『音』として、捉えていますが、お魚達には、どのように感じられてるのでしょうね?(笑)
マッドソニック論・・・
私が思うに、究極?!は、『動かす(側線を刺激)』か、『何もしない(視覚を刺激)』か、ですかね。
同じコンディションで、同じルアーを投げて、一方は『リトリーブ』、もう一方は『ホットケ』、でどちらがお魚を良く誘うか?
多分状況(プレッシャーとか)によって、マチマチになると思いますが・・・(笑)
人間は振動を『音』として、捉えていますが、お魚達には、どのように感じられてるのでしょうね?(笑)
こんにちはひろpさん。
プラグやワーム(まあ鱒釣りには使いませんが)の表面仕上げ(凹凸のある模様もふくむ)でもしかすると魚へのアピールの仕方が違ってたりすると思いません?
細かいところでは同じプラグやスプーンでもツルっとした物とマット仕上げでは、同じ引いても出ている波動が違うと思うんですよ。
マットの場合、普通は見た目に反射光が少ないだけに思えますが、音波(波動)系に関しても何か違いがあるような。
それから、魚の聴覚としては側線が有名なのですが、魚種にもよりますが側線以外の聴覚器官が発達しているものがいるようです。(内耳の存在や浮き袋が受ける振動など)
側線は、魚の体側にそってズバっと走っていることでもわかるように、音というより水圧や流れといったことの感知が主たる役割ではないかと言われていることも見たように思います。
プラグやワーム(まあ鱒釣りには使いませんが)の表面仕上げ(凹凸のある模様もふくむ)でもしかすると魚へのアピールの仕方が違ってたりすると思いません?
細かいところでは同じプラグやスプーンでもツルっとした物とマット仕上げでは、同じ引いても出ている波動が違うと思うんですよ。
マットの場合、普通は見た目に反射光が少ないだけに思えますが、音波(波動)系に関しても何か違いがあるような。
それから、魚の聴覚としては側線が有名なのですが、魚種にもよりますが側線以外の聴覚器官が発達しているものがいるようです。(内耳の存在や浮き袋が受ける振動など)
側線は、魚の体側にそってズバっと走っていることでもわかるように、音というより水圧や流れといったことの感知が主たる役割ではないかと言われていることも見たように思います。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。