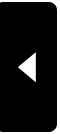前アタリ3
この記事を初めてお読みになる方は、前回、前々回の記事「前アタリ1」「前アタリ2」をお読みになることを強くおすすめいたします。
なお、以下の文章で使われる「前々アタリ」とは「前アタリの前アタリ」のことを指しています。
-------------------------
前々アタリを検証する
前回の記事では、引いているルアーの正面に当たる流れだけでなく、後ろにできる乱流も引き抵抗になるという話を中心に書きました。
これはルアーの後ろ側にできる乱流の状態が変われば、引き抵抗も変わるということを意味しています。
それでは次に下の画像を見てください。
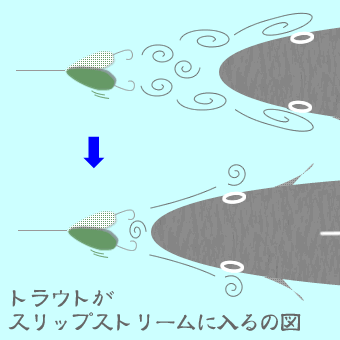
これはスプーンを追尾してきたトラウトがスプーンの後ろ側の乱流に入るという状態です。
スプーンの後ろの乱流をスリップストリームと呼ぶ事もありますね。
上の方はスプーンとトラウトの距離があり、下の状態ではかなり接近しております。これはサイトで釣り込んだ方であればどちらもおなじみの状態ですよね。
下の状態ではトラウトのボディによって乱流の状態にかなりな変化をきたすことは容易に理解できることでしょう。
多くの場合、ルアーの後ろの乱流が、文字どおり流線型をした魚のボディーによって整流されています。
この変化って竿を持ってリール巻いている人にわからんでしょうか???
図解ではスプーンを取り上げましたが、クランクでも同じです。
むしろ、クランクのようにはっきりとしたバイブレーションを発生させるルアーでは、トラウトが後ろについたときの「引き感覚」に大きな変化を生じることが多いようです。
実際のところクランクの場合は一般的に引き抵抗が小さくなる方へ変化します。
クランクのリトリーブを、ラインとロッドに角度を持たせる方法で行なっているならば、クランクの後ろにトラウトが付いて引き抵抗が減り、ロッドチップの曲がり具合が減少するという現象でこれが現れます。
ただし、引いているルアーが起こしている乱流の状態やトラウトの大きさや付き方により、感じる変化の程度は様々です。
あまりにトラウトが小さい場合は変化の度合いも小さいか、またはほとんど影響がないこともあるでしょう。
「確かに理屈ではそうかも知れん」
「が、しかし手元にまでそんな情報が伝わるのだろうか?」
「いや伝わらん、わかるとすればそりゃ霊感だ霊感」
「あ、いや私普通にわかりますけど・・・」
「ウソつけアホ!脳内にもほどがあるぞ!」
■脳内実験
ここまで書いても、引いているルアーの直後にトラウトが入っても「わからないだろう」と思っている人のために、ひとつの思考実験をしてみます。
前回の記事「前々アタリ」ではクランクやスプーンの引き抵抗について書きました。
クランクやスプーンは、そのデザインによって様々な引き抵抗があり、その違いはけっこうわかるという話です。
それでは、引き抵抗に違いがあると思われるクランク2種か、またはスプーン2種を自分の手持ちの中から選ぶことができるでしょうか?
今は思い出せなくても、現場で実際に引けば違いがわかりそうだと思うルアーでも良いですよ。
そして、それら2種類のルアーのどちらかを引いていることを想像してみてください。
例えば、「引き抵抗が大きい」ルアーAを引いているとしましょう。
次に架空の状況ではありますが、そのルアーAが突然に「引き抵抗の小さい」ルアーBに変わったとしましょうや。
この変化ってわかると思いますか?
むしろこれってA、Bを個別に結び直して引くよりも、もっとわかりやすい変化の仕方だと思いませんか?あくまで仮想的な脳内実験ではありますが。
それじゃあ、上の画像のように、トラウトが近づいてきてルアーの直後にフッと付いたとしたら、ロッドを持ってリールを巻いてる人はそれに気付くことができるでしょうか???
■乱流の変化を感じる様々なケース
これまでに、引いているルアーの後ろにトラウトが付けば乱流の状態が変わって引き抵抗も変わることを書いてきました。
以下には現実問題として乱流変化がどんな場合に起きるのか列挙しておきます。
(1)トラウトがルアーの直後に入る瞬間
安定してウォブリングしていたルアーの直後にフッとトラウトが入ると、乱流の状態が突然変化する。
文字で書けば「フルン,」という感じになるかも知れない。
トラウトがどれくらいまで近づくと変化が出るかはルアーと、トラウトの入り方による。
トラウトが急激に入った方が変化はつかみやすくゆっくり近づいてそろりと入った場合には変化に気付きにくいかも知れない。
また、ルアー後方のどれくらいにトラウトが付くと乱流が急激に変化するかは、いわゆる「しきい値」のようなものがある。
例えば、3cm以内に入ると急に変化するが、それ以上だとほとんど変化なしといった感じだ。
(2)トラウトがルアーの直後から離れる瞬間
これは明らかに1)の逆パターン。同じく乱流の状態は変化する。トラウトがついていなかった状態に戻るための変化。
(3)トラウトがルアーの直後を一定間隔を保って追尾する
ことによっては数秒間にわたり、本当にきっちりと追尾していることもある。これはスッピンでルアーを引くのとは異なる形での乱流をずっと体験することになる。
たとえて言えば、リトリーブする側にとってはスプーンのタイプを突然替えたのと同じような変化をもたらしている。
クランクでは特に引き抵抗が弱まる反応になることが多い。
スプーンでは引き抵抗の変化だけでなく、元々安定したウォブリングをする性質を持ったものが不安定な感じになったりもする。
ことによって不規則なウォブリングが断続的に発生する場合にはリトリーブが重く感じることもある。
ただし、ルアーと魚の距離、魚の大きさ、ルアーそのものの性質などの諸条件によって、どの程度の乱流変化があるかは様々だ。
また、釣り人にそうとわかるほど乱流変化を起こすか起こさないかは(1)で述べた「しきい値」のようなことがある。
ルアーの後ろに魚がついてもわからないという人は、引き抵抗に変化をもたらす諸条件が「しきい値」に達していない状態の経験が多い可能性がある。
使っているルアー、魚の平均サイズ、引いている距離、そしてその日の魚の気分など条件は様々だ。
(4)上の(1)〜(3)の混成状態
一回のリトリーブで上の(1)〜(3)の状態が無秩序に発生する場合がある。トラウトが付いたり離れたり。また単独でのトラウトでなく、複数が入れ替わって追尾している場合などにも起こる。
直接のバイトはないにせよ、ある意味は生命反応ぽい感じがある。まさに釣れそうな感じだ。
以上、トラウトがルアーを追尾する関係で発生する「前々アタリ」について書きました。
ところが、この「前々アタリ」というのは魚がまったくルアーに接触していない関係もあり、確かにかなり微妙なものです。
そして微妙であるだけに、魚とは直接関係ない反応を得てしまうこともあり、場合によってはそれを「前々アタリ」に勘違いしているという考えもあります。
次回予定の「前アタリ4」ではそのことについて触れる予定です。
(注意)
この前々アタリ、「誰にもわかるはずだ」とはあえて書きません。
前アタリ4に続く
なお、以下の文章で使われる「前々アタリ」とは「前アタリの前アタリ」のことを指しています。
-------------------------
前々アタリを検証する
前回の記事では、引いているルアーの正面に当たる流れだけでなく、後ろにできる乱流も引き抵抗になるという話を中心に書きました。
これはルアーの後ろ側にできる乱流の状態が変われば、引き抵抗も変わるということを意味しています。
それでは次に下の画像を見てください。
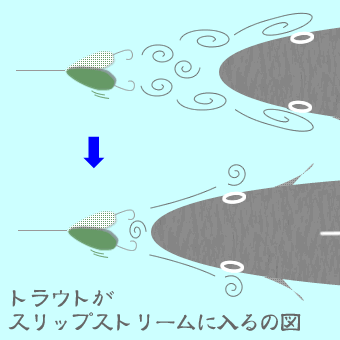
これはスプーンを追尾してきたトラウトがスプーンの後ろ側の乱流に入るという状態です。
スプーンの後ろの乱流をスリップストリームと呼ぶ事もありますね。
上の方はスプーンとトラウトの距離があり、下の状態ではかなり接近しております。これはサイトで釣り込んだ方であればどちらもおなじみの状態ですよね。
下の状態ではトラウトのボディによって乱流の状態にかなりな変化をきたすことは容易に理解できることでしょう。
多くの場合、ルアーの後ろの乱流が、文字どおり流線型をした魚のボディーによって整流されています。
この変化って竿を持ってリール巻いている人にわからんでしょうか???
図解ではスプーンを取り上げましたが、クランクでも同じです。
むしろ、クランクのようにはっきりとしたバイブレーションを発生させるルアーでは、トラウトが後ろについたときの「引き感覚」に大きな変化を生じることが多いようです。
実際のところクランクの場合は一般的に引き抵抗が小さくなる方へ変化します。
クランクのリトリーブを、ラインとロッドに角度を持たせる方法で行なっているならば、クランクの後ろにトラウトが付いて引き抵抗が減り、ロッドチップの曲がり具合が減少するという現象でこれが現れます。
ただし、引いているルアーが起こしている乱流の状態やトラウトの大きさや付き方により、感じる変化の程度は様々です。
あまりにトラウトが小さい場合は変化の度合いも小さいか、またはほとんど影響がないこともあるでしょう。
「確かに理屈ではそうかも知れん」
「が、しかし手元にまでそんな情報が伝わるのだろうか?」
「いや伝わらん、わかるとすればそりゃ霊感だ霊感」
「あ、いや私普通にわかりますけど・・・」
「ウソつけアホ!脳内にもほどがあるぞ!」
■脳内実験
ここまで書いても、引いているルアーの直後にトラウトが入っても「わからないだろう」と思っている人のために、ひとつの思考実験をしてみます。
前回の記事「前々アタリ」ではクランクやスプーンの引き抵抗について書きました。
クランクやスプーンは、そのデザインによって様々な引き抵抗があり、その違いはけっこうわかるという話です。
それでは、引き抵抗に違いがあると思われるクランク2種か、またはスプーン2種を自分の手持ちの中から選ぶことができるでしょうか?
今は思い出せなくても、現場で実際に引けば違いがわかりそうだと思うルアーでも良いですよ。
そして、それら2種類のルアーのどちらかを引いていることを想像してみてください。
例えば、「引き抵抗が大きい」ルアーAを引いているとしましょう。
次に架空の状況ではありますが、そのルアーAが突然に「引き抵抗の小さい」ルアーBに変わったとしましょうや。
この変化ってわかると思いますか?
むしろこれってA、Bを個別に結び直して引くよりも、もっとわかりやすい変化の仕方だと思いませんか?あくまで仮想的な脳内実験ではありますが。
それじゃあ、上の画像のように、トラウトが近づいてきてルアーの直後にフッと付いたとしたら、ロッドを持ってリールを巻いてる人はそれに気付くことができるでしょうか???
■乱流の変化を感じる様々なケース
これまでに、引いているルアーの後ろにトラウトが付けば乱流の状態が変わって引き抵抗も変わることを書いてきました。
以下には現実問題として乱流変化がどんな場合に起きるのか列挙しておきます。
(1)トラウトがルアーの直後に入る瞬間
安定してウォブリングしていたルアーの直後にフッとトラウトが入ると、乱流の状態が突然変化する。
文字で書けば「フルン,」という感じになるかも知れない。
トラウトがどれくらいまで近づくと変化が出るかはルアーと、トラウトの入り方による。
トラウトが急激に入った方が変化はつかみやすくゆっくり近づいてそろりと入った場合には変化に気付きにくいかも知れない。
また、ルアー後方のどれくらいにトラウトが付くと乱流が急激に変化するかは、いわゆる「しきい値」のようなものがある。
例えば、3cm以内に入ると急に変化するが、それ以上だとほとんど変化なしといった感じだ。
(2)トラウトがルアーの直後から離れる瞬間
これは明らかに1)の逆パターン。同じく乱流の状態は変化する。トラウトがついていなかった状態に戻るための変化。
(3)トラウトがルアーの直後を一定間隔を保って追尾する
ことによっては数秒間にわたり、本当にきっちりと追尾していることもある。これはスッピンでルアーを引くのとは異なる形での乱流をずっと体験することになる。
たとえて言えば、リトリーブする側にとってはスプーンのタイプを突然替えたのと同じような変化をもたらしている。
クランクでは特に引き抵抗が弱まる反応になることが多い。
スプーンでは引き抵抗の変化だけでなく、元々安定したウォブリングをする性質を持ったものが不安定な感じになったりもする。
ことによって不規則なウォブリングが断続的に発生する場合にはリトリーブが重く感じることもある。
ただし、ルアーと魚の距離、魚の大きさ、ルアーそのものの性質などの諸条件によって、どの程度の乱流変化があるかは様々だ。
また、釣り人にそうとわかるほど乱流変化を起こすか起こさないかは(1)で述べた「しきい値」のようなことがある。
ルアーの後ろに魚がついてもわからないという人は、引き抵抗に変化をもたらす諸条件が「しきい値」に達していない状態の経験が多い可能性がある。
使っているルアー、魚の平均サイズ、引いている距離、そしてその日の魚の気分など条件は様々だ。
(4)上の(1)〜(3)の混成状態
一回のリトリーブで上の(1)〜(3)の状態が無秩序に発生する場合がある。トラウトが付いたり離れたり。また単独でのトラウトでなく、複数が入れ替わって追尾している場合などにも起こる。
直接のバイトはないにせよ、ある意味は生命反応ぽい感じがある。まさに釣れそうな感じだ。
以上、トラウトがルアーを追尾する関係で発生する「前々アタリ」について書きました。
ところが、この「前々アタリ」というのは魚がまったくルアーに接触していない関係もあり、確かにかなり微妙なものです。
そして微妙であるだけに、魚とは直接関係ない反応を得てしまうこともあり、場合によってはそれを「前々アタリ」に勘違いしているという考えもあります。
次回予定の「前アタリ4」ではそのことについて触れる予定です。
(注意)
この前々アタリ、「誰にもわかるはずだ」とはあえて書きません。
前アタリ4に続く
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。